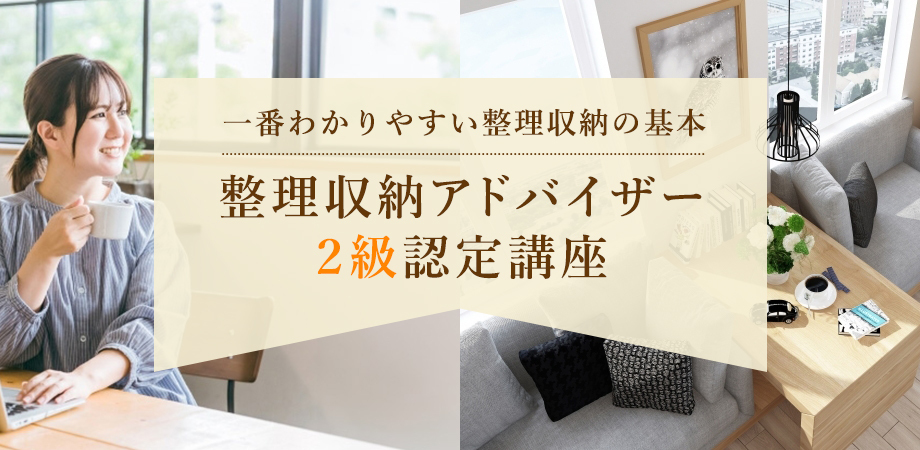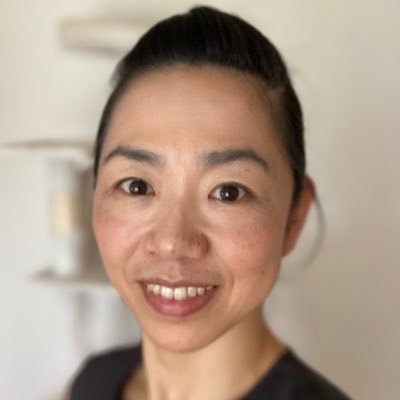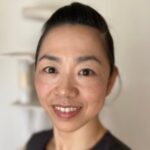毎日ストレス…「片付けなさい!」を卒業する3つのヒント


うちの子、私が片付けてっていわないと、自分から片付けようとしないんです…毎日毎日言ってるのに。

片付けてって言ったら片付けるんですよね?それは素晴らしいですよ!

えっ、そうなんでしょうか。でも、やっぱり自分から片付けてほしいんです…

その気持ちもわかりますよ!では今回は、片付けのノウハウではなく、考え方のお話しをしますね!
親は「子どもが片付けをしない」「言わないとやらない」ことでストレスを感じやすいもの。でも、無理に「片付けさせる」と考えるよりも、子どもと一緒に楽しく取り組むことが大切です。
今回は、子どもに片付けを促す前に見直したい「3つのチェックポイント」と具体的な解決方法をお伝えします。
まず、最初にお伝えしたいことは、これをやれば100%子どもが片付けられるようになる!という魔法の方法ではありません。ただ、子どもが片付けを自然に身につけるためには、親自身の「心の持ち方」や「関わり方」が大事だということです。
1. 片付けのハードルを親が決めていない?
「毎回言わないと片付けない…」と悩む親御さんは多いです。でも、こう考えてみましょう。「毎回声をかければ片付けるなら、それはすごいこと!」
そもそも片付けは、人間の自然な本能には含まれていません。食べる、寝る、排泄する…これらは生まれつき備わった欲求ですが、「片付ける」は学んで身につけるものです。だからこそ、声をかけたらできる、というだけで十分素晴らしいのです。
片付けが苦手な子を見て、「最後まできちんと片付けないと意味がない」と思ってしまう方もいます。でも、片付けは一度に完璧を求めるよりも、「一つでもできたらOK」とハードルを下げることが大切です。
たとえ、言われてしぶしぶと片付けたとしても、片付けられたことには代わりはないのですがら、そこは褒めてあげましょう。そして、少しずつ「片付けるのって気持ちいいな」と思えるようになっていくのです。
そのうちに、自分から片付けができたときはすかさずいつもの倍、褒めてあげましょう。
2. 一緒に楽しんでお片付けをしていますか?
「私自身、片付けが苦手なんです…」というお母さんも多いです。でも、それは一旦脇に置いておきましょう。
片付けを楽しく習慣化させるためには、親も一緒に楽しむ姿勢が大切です。例えば、
「お片付けゲーム!ママとどっちが早く終わるかな?」
「このおもちゃたちをおうちに帰してあげようね!」
このように、ゲーム感覚や遊び心を取り入れると、子どもは自然と片付けに取り組むようになります。
また、「一緒にやる」ということ自体が、親子のコミュニケーションにもなります。親子の片付けで大切なのは「早く終わらせること」や「完璧にすること」ではなく、「習慣をつけること」です。だからこそ、焦らず、子どもと一緒に取り組んでみましょう。
3. 片付ける場所は決まっていますか?
「片付けなさい」と言っても、子どもが動かない場合、「片付ける場所」が決まっていない可能性があります。片付けの場所が曖昧だと、子どもはどうすればいいか分からず、結果として片付けが進まないのです。
そんな時は、子どもと一緒に片付ける場所を決めましょう。
「このおもちゃはどこに置こうか?」
「ブロックのおうちはここにしよう!」
と、子ども自身に場所を決めさせることで、「自分で決めた」という自覚が生まれ、片付けることに責任感を持つようになります。
また、片付けのハードルを下げる工夫も大切です。例えば、よく使うおもちゃはリビングの一角に置くなど、すぐに片付けられる場所を設定すると、子どもも片付けやすくなります。
「片付けるのが大変」と感じるのは、作業が難しいからです。片付けやすい仕組みを作ることで、自然と片付けが習慣化していきます。
まとめ
子どもに片付けを教えるための3つのポイントは次の通りです。
- 片付けのハードルを下げること
- 一緒に楽しみながら取り組むこと
- 片付ける場所を明確に決めること
片付けは親子のコミュニケーションの場でもあります。「うまくいかないな」と感じた時は、「次はこうしてみよう」と試行錯誤を繰り返してみてください。
「今日はブロックだけ片付けられたね!」 「ママと競争して楽しかったね!」
そんな日々の小さな積み重ねが、子どもにとっても親にとっても大きな成長につながります。
毎日の片付けは、子どもの成長だけでなく、親の成長にもつながる大切な時間です。焦らず、楽しみながら取り組んでいきましょう。

親子の片付けで大切なのは「早く終わらせること」や「完璧にすること」ではなく、「習慣をつけること」、ですか・・・
私、早く!とか、ちゃんとやって!って言っちゃってました・・・

上手に片付けることを学ばせるよりも、やると気持ちが良いとうことを覚えてもらいましょう!ぜひ、親子で楽しみながら!