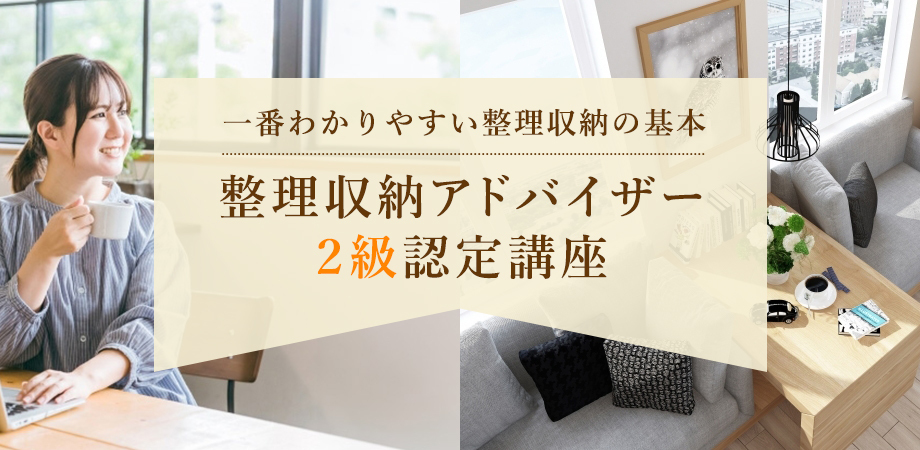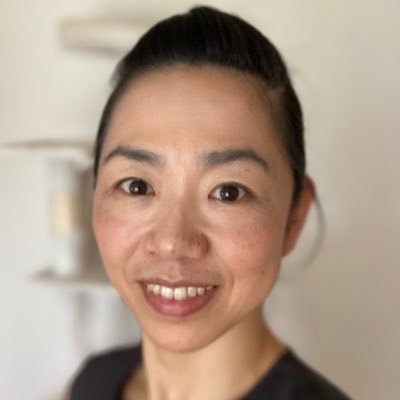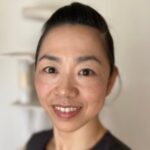「捨てる」より大事なこと~子どもに伝えたい、整理の本質

子どもの持ち物、どうしたらいいんでしょうか。全然捨てたがらないんです~

それ、よくあるお悩みですよ。でも、“捨てること”をゴールにしなくていいんです。

えっ?でも、整理っていらないものを捨てることじゃないんですか?

捨てることも整理の一つですが、子どもにとって大切なのは
“必要かどうかを考える経験”を重ねることなんです。
子どもに「整理」を教えるとき、大切にしたいこと
最近よく、「捨てる=正しい」という空気を感じることがあります。
SNSや雑誌でも「手放してスッキリ!」という言葉が並び、「モノが少ない=心地いい」みたいな風潮も。
もちろん、不要なものを手放すことは心や暮らしにゆとりをもたらします。でも、それはあくまで“結果”であって、“目的”ではありません。
特に、子どもに整理の方法を教えるときには、そこを忘れないようにしたいのです。
「捨てなきゃ」と思わせない関わり
学期の節目には、プリント類や教材、お道具、お祝いにもらったプレゼントなど、子どもの持ち物が一気に増えます。
親としては「早く片付けてスッキリさせたい」と思ってしまいがち。
でも、「捨てようね」と言ってしまうと、子どもにとっては大切な宝物を否定されたように感じることも。
そんなときこそ大切にしたいのが、“必要かどうかを自分で考える経験”を子どもに持たせることです。
5歳の末っ子と「おもちゃの整理」
末っ子が5歳だった頃、一緒におもちゃの整理をしました。
「よく遊ぶおもちゃ」と「最近あまり遊んでいないおもちゃ」
この2つに分ける、とてもシンプルな方法です。
この時期の息子は、「使っている・いない」の判断が感情に大きく左右される年齢でした。だからこそ、「取っておきたい」という気持ちも尊重しました。

このとき私が意識したのは、「捨てるための整理」ではなく、「考えるための整理」にすること。
「これ、まだ好き?」
「また遊びたいと思う?」
と問いかけながら、子どもが自分で考える時間を大切にしました。
小学3年生と「引き出しの整理」
長男が小学3年生の頃に引き出しの中を整理したときのことです。
まずは中身をすべて出して、空っぽになった引き出しを掃除。

「うわー、スッキリ!」と声を上げる長男に、「気持ちいいね~」と声をかけながらスタート。
そして、一つひとつ手に取って、
- よく使っているもの
- たまに使うもの
- 使っていないもの
に分けていきます。
中には「もう使ってないけど、なんか好きなんだよね…」というものも。
そんなとき、「じゃあ捨てようか」とは言いません。
「その気持ち、いいね!」と受け止めながら、「どうしたいと思う?」と問いかけました。
このやりとりこそが、整理の本質。
”必要かどうかを考える“経験”が、子どもにとっての大きな学びになるのです。
褒め方にもひと工夫
整理が終わったあと、子どもが「これはもう使ってないから、捨てる」と言ったとき、親としては「すごい!捨てられたね!」と褒めたくなります。
でも私は、そこを少しだけ工夫しています。
「ちゃんと考えて決められたんだね」
「いままでありがとうって言えたの、優しいね」
そんなふうに、“捨てたこと”ではなく、“考えたこと”“決めたこと”を褒めるようにするのです。
大人の目から見ると、「これ、いらないでしょ」と思ってしまうモノでも、子どもにとっては意味のある存在であることも多いのです。
だからこそ、「自分で考えて決める」プロセスが一番大事なのです。
整理=人生を選ぶ練習
なんて、大げさな見出しですが、あながち大げさでもないんです。
モノの整理を通して、必要・不必要を判断できるようになるのですから、そもそも大切なことは、「自分にとって必要かどうかを考える時間を、ちゃんと持つこと」だと思うのです。
その積み重ねが、将来、人間関係や時間の使い方、仕事や進路など、さまざまな選択に直面したときに、自分の心の声に耳を澄ませる力になっていきます。
小さな引き出しひとつを整理することが、実は人生の選択の土台を育てている――そう思うと、ちょっとワクワクしませんか?

なるほど…。うちの子にも、“必要かどうか”を考える時間を大事にしてあげたいです。今度の休みに一緒にやってみます!

それ、いいですね。大人にとってもきっと、新しい発見があると思いますよ
まずは、お子さんと一緒に、身近なところから。
例えば、おもちゃ箱でも、文房具でも。
「これは今も使ってる?」
「どうして取っておきたいと思うの?」
そんな問いかけを通して、お子さんの小さな選択の経験を、ひとつひとつ応援していきましょう。あなたのその姿勢が、子どもにとってなによりの学びと喜びになるはずです。